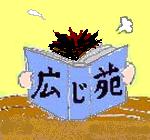
先日、小学館のポケットサライという新書のシリーズの1冊、「日本庭園の見方」という本を買った。中身は写
真が多くて面白い本なのだが、副題の「歴史がわかる、腑に落ちる」の「腑に落ちる」が、どうにもひっかかる。
「腑に落ちない」はごく自然だが、「腑に落ちる」には違和感がある。自分の文中では決して使わないが、新書のタイトルに使われているということは、ふつうの言い方なのだろか? それとも、読者にざらっとした引っかかりを与えるための手法なのか?
こういうときには私同様ことば好きの夫に、まず聞いてみる。
「ねえ、腑に落ちるって、使う?」
「ぼくは使わないな。納得がいくという意味で、あえて使うなら、『胃の腑に落ちる』かな」
次にインターネットで調べてみる。検索エンジンのキーワードに「腑に落ちる」を入れて検索するとけっこう出てくる。ということは、ふつうの言い方なのかと思いながら、そのひとつに入ってみる。そこの解説によると「辞書の多くは否定形の形『落ちない』しか載せない。肯定の場合は『心に落ちる、胸に落ちる』を使う」のだそう。ただし、「腑に落ちる」もかなり使われているので、誤用と言えるかどうかわからないと書いてある。
やはり、「腑に落ちる」は少しヘンなんだ。「心や胸に落ちる」も私は使わない、使うとしたら「納得できる」だろうと私は納得した。ところが、その矢先、「エドワード・ゴーゴリーの世界」(河出書房新社)という本を読んでいたら、鼎談のなかで「すごく腑に落ちたんです」(濱中利信)「非常に腑に落ちました」(江國香織)という会話を見つけた(3人目のゴーゴリーの翻訳者・柴田元幸さんは使っていなかったが)。小学館や河出書房の編集者がOKしたということは、「腑に落ちる」の認知は進んでいるのだろう。